孟子「おめでとうございます。王者まであと一歩です。」
孟子・原文
莊暴見孟子、曰:「暴見於王、王語暴以好樂、暴未有以對也。」曰:「好樂何如?」
孟子曰:「王之好樂甚、則齊國其庶幾乎!」
他日、見於王曰:「王嘗語莊子以好樂、有諸?」王變乎色、曰:「寡人非能好先王之樂也、直好世俗之樂耳。」
曰:「王之好樂甚、則齊其庶幾乎!今之樂猶古之樂也。」曰:「可得聞與?」
曰:「獨樂樂、與人樂樂、孰樂?」曰:「不若與人。」
曰:「與少樂樂、與眾樂樂、孰樂?」曰:「不若與眾。」
孟子・書き下し
莊暴孟子に見えて曰く、「暴王於見えるに、王暴に語るに樂を好むを以う、暴未だ對えを以うる有らざる也。」曰く、「樂を好むこと何如」 と。
孟子曰く、「王之樂を好むこと甚しからば、則ち齊國其れ庶幾き乎」と。
他日、王於見えて曰く、「王嘗て莊子に語るに樂を好むを以てすと。諸れ有るか」と。王色乎變えて曰く、「寡人能く先王之樂を好むに非る也、直だ世俗之樂を好む耳」 と。
曰く、「王之樂を好むこと甚しからば、則ち齊其れ庶幾き乎。今之樂、猶お古之樂のごとき也」と。曰く、「得て聞く可き與」 と。
曰く、「獨り樂を樂しむと、人與樂を樂しむと、孰れか樂しき」と。曰く、「人與に若か不」 と。
曰く、「少き與樂を樂しむと、眾き與樂を樂しむと、孰れか樂しき」と。曰く、「眾き與に若か不」 と。
孟子・現代語訳
(斉の宣王の家臣である)荘暴が、孟子に会って言った。「私が宣王様に目通りしますと、王様は”ワシは音楽が好きじゃ。(どう思う)”と仰せでした。私はうまく返事が出来ませんでした。」孟子「…。」荘暴「王様が音楽を好むのは、はたしていかがなことでしょう。」
孟子「ふむ、王様が深く音楽をお好みなら、斉国は繁栄に近づいておりますぞ。」
その後別の日に、孟子が宣王に会って言った。「王様は以前、荘暴どのに”音楽が好きだ”と仰せになったと聞きました。本当ですか?」
宣王は顔色を変えて言った。「いやそのあれだ、ワシは古の聖王様の音楽はどうにも好きになれぬ。ただ世間の、俗な音楽を好んでいるだけじゃ。(古典音楽の講義などまっぴらじゃぞ。)」
孟子「おめでとうございます。王様がそこまで音楽にご執心なら、斉国は繁栄に近づいております。今どきの流行りの歌も、古の聖王の音楽と違いはありませぬ。」
宣王「ほうほう、どういうわけじゃ?」
孟子「王様は、一人で音楽を楽しまれるのと、誰かと共に楽しむのと、どちらがよろしいですか?」
宣王「それは誰かと一緒がいいに決まっておる。」
孟子「ではごく少人数で楽しむのと、大勢で楽しむのと、どちらがよろしいですか?」
宣王「それは大勢がいいに決まっておる。」
孟子・訳注
莊暴:斉の宣王の家臣だという。
樂:小林本にいう。「宋の陳善の捫蝨新話いう、楽はまさに悦楽の楽のように読まねばならぬ。世人が礼楽の楽のように読むのは誤りである。荘暴のこの章は、ただ鼓樂だけが字のごとく読むべきだが、その他はみな悦楽の楽である。郝氏孟子解もまたいう、楽楽とはちょうどその楽しみを楽しむというのと同じ。その楽とは、すなわち下文の鼓楽がその一つで、田猟がまたその一つである。おもうに、通説は楽を音楽と解するが、今は陳・郝二氏に従って音楽と狩りの二つを含めて娯楽・歓楽のように解しておいた」。
訳者は通説に従った。
曰好樂何如:小林本に「語の端をかえたので、曰の字を重ねたのである」とあるが、「語の端」とは何のことか分からない。口調のことだろうか? 確かに「暴見於王」部分は一人称に自分のいみ名=暴を使っているので、謙遜した表現と分かる。
庶幾:庶は「ちかし」とよみ、「おおかた」「ほとんど」と訳す。状況・程度に接近する意を示す。「回也其庶乎=回やそれ庶(ちか)きか」〈回(顔淵)はまあ(理想に)近いね〉〔論語・先進〕。
幾も「ほとんど」「~にちかし」とよみ、「すんでのところで」「あやうく」「ほとんど」と訳す。ある状況・程度に接近する意を示す。「今吾嗣為之十二年、幾死者数矣=今吾嗣(つ)いでこれを為すこと十二年、幾(ほとん)ど死せんとする者数(しば)しばなり」〈今私が跡を継いでこの仕事を十二年している、あやうく死にかけたことは何度もあった〉〔柳宗元・捕蛇者説〕
- (ショキ)希望する。
- (コイネガワクハ)・(コイネガウ)ぜひ望むことは。どうか…であってほしい。「庶幾息兵革=庶幾(こひねが)はくは兵革を息(や)めんことを」〔史記・秦始皇〕
- (チカシ)まもなくそうなりそうだ。のぞましい状態にちかい。「斉国其庶幾乎=斉国は其れ庶幾からん乎」〔孟子・梁下〕
王變乎色:「色」は表情、顔色。昔の聖王を持ち出した音楽講義などされてはたまらない、と王が思ったのである。孟子の古いもの好き、説教好きにうんざりしていたのだろう。


莊子:孟子(BC372?-BC289)と、老荘思想家の一人である荘子(BC369?-BC286)はほぼ同時期を生きた人だが、ここでは冒頭に登場の荘暴に対する敬称。
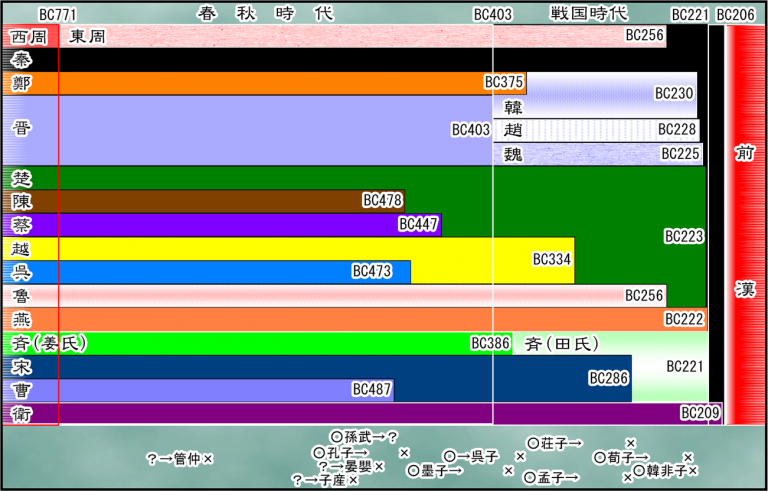
孟子・付記
思案中


コメント